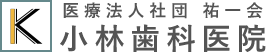親知らずについて
親知らずは抜くべき?残すべき?
 「やっぱり親知らずは抜いた方がいいですか?」
「やっぱり親知らずは抜いた方がいいですか?」
こうしたご質問をよくいただきます。親知らずは、放置すると腫れたり痛んだりすることがあると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、すべての親知らずが抜歯対象というわけではありません。周囲の歯や歯茎に悪影響を与えない場合は、将来のためにあえて残しておくことが推奨されることもあります。
親知らずの状態は、歯並びや噛み合わせ、骨や歯茎の健康にも関わります。気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
抜歯が必要な親知らずのケース

親知らずについて、「抜いたほうがいいのか迷っている」という方は少なくありません。実際には、すべての親知らずを抜く必要はなく、健康に問題がなければ残しておくことも可能です。しかし、次のような状態の場合は抜歯を検討した方が良いことがあります。気になる方は、ぜひ当院にご相談ください。
半分だけ生えている(部分萌出)
歯茎から半分だけ出ている親知らず(部分萌出)は、磨きにくく炎症が起きやすいです。腫れや痛みを繰り返す場合は抜歯を検討する必要があります。
斜めや横向きに生えている(水平埋伏・斜位埋伏)
斜めや横向きに生えている親知らず(水平埋伏・斜位埋伏)は、隣の歯を押して歯並びを乱したり、むし歯・歯周病の原因になります。
手前の歯を押している
親知らずが手前の歯に強く押し当てられていると、歯並びや噛み合わせに悪影響を与えることがあります。
噛み合わず粘膜を傷つけている
上下で噛み合わない親知らずは伸びて歯茎や頬の粘膜を傷つけることがあります。痛みや顎関節への負担の原因にもなることがあります。
嚢胞ができている(含歯性嚢胞)
埋まった親知らずの周囲に袋状の影(含歯性嚢胞)ができることがあります。放置すると周囲の骨や歯にトラブルを引き起こす可能性があります。
むし歯や歯周病になっている
親知らずは磨きにくいため、むし歯や歯周病が進行しやすい歯です。進行している場合は抜歯が推奨されます。
親知らずのQ&A
親知らずとは、どんな歯ですか?
一番奥に生える歯を「親知らず」といい、前歯から数えると8番目の歯です。
親知らずの正式名称は「第3大臼歯」です。成人してから生えることが多い親知らずという歯は、親も生えたことを知らないということから「親知らず」と呼ばれています。
親知らずは上下左右で1本ずつ、合計すると4本あります。
親知らずは必ず抜かないといけませんか?
必ず抜かなければいけない、ということではありません。
- 親知らずが横に埋まっている
- 親知らずの一部のみ歯茎から出ている
以上のような場合は、抜歯をお勧めしております。なぜかというと、そのまま放置しておくと歯茎が腫れたり、痛んだりする可能性があるからです。
また、親知らずのケアが十分に出来ないことで隣の歯のむし歯リスクを高めてしまうことが考えられるため、抜歯をした方がメリットは多いです。
周囲の歯が痛み出したのはなぜでしょうか?
炎症を起こしている可能性があります。
完全に埋まった状態の親知らずでも細菌が歯と歯茎の隙間から入り込んでしまうことがあり、細菌感染によって炎症を起こし、腫れや痛みが出る場合があります。早めに治療を行うようにしましょう。
痛み・腫れの他にも症状はありますか?
親知らずの炎症は、さまざまなトラブルを引き起こす原因になります。
炎症が広がると、以下のような症状が現れることがあります。
- 口を開閉する時に痛み、動かしにくくなる
- 喉が痛む
- 首の方に炎症が及んだ場合、首が腫れる
炎症が喉の奥にまで広がれば、気道を塞いでしまうこともあります。それによって呼吸困難となり、重篤な状態に陥ってしまう可能性も全く無いという訳ではありません。悪化してしまう前に早めに歯科医院を受診しましょう。
抜かずに治療できますか?
問題を根本的に解決するためには、抜歯を伴う治療が必要です。
親知らずの痛みは、細菌が増殖したことが原因である場合が多いです。痛みが強く出ている場合は抗生物質によって軽減できますが、これは一時的に細菌が減っただけであり、対症療法でしかありません。
時間が経てばまた細菌は増殖し、痛みが生じる可能性は十分あります。抜歯を行うことで、細菌が溜まってしまう環境を無くすことができます。
激しく痛むため、すぐに抜歯したい
抜歯の前に、まずは炎症を抑える処置が必要です。
激しく痛む原因は炎症です。ですからまずは炎症を抑えることが必要となります。炎症を抑えないまま抜歯をしてしまうと、抜歯後で更に炎症が悪化してしまう可能性があります。また、患者様の中には強い炎症によって麻酔が効きにくくなってしまう方もいらっしゃいます。
激しく痛む場合はまずは炎症を抑えるため、抗生物質を服用しましょう。そして炎症が治まったのを確認した後で抜歯を行います。
抜歯後は腫れや痛みがありますか?
抜歯の際は麻酔をかけるため痛みはほとんどありませんが、抜歯後は必ず腫れが生じます。
抜歯の際は痛みを抑えるため、しっかり麻酔を効かせてから抜歯を行います。
当院では表面麻酔と、更に極細の注射針を使って麻酔を行うことで、麻酔時の痛みを最小限に抑えています。また、抜歯中に痛みを感じた場合もお知らせいただければすぐに麻酔を追加し、痛みの無い状態になってから治療を再開しますのでご安心ください。
腫れ方には個人差がありますが、抜歯後はほとんどの場合で腫れが生じます。治療翌日〜翌々日が腫れのピークで、それからは徐々に治まっていきますので心配ありません。
【注意】
大切な面接がある、旅行や出張の予定が入っている、お仕事のプレゼンテーションがあるなど、抜歯後で大切な予定が入っているという場合は、抜歯はお勧めしていません。
腫れ・痛みが長引いてしまった場合を考慮し、抜歯後10〜15日は大事な予定がないタイミングを選んで抜歯を行うようにしましょう。
親知らずは神経の近くにあると聞いてから、歯を抜くのに不安を感じています。
下顎の骨の中には下顎管という管があり、この中には下歯槽神経と血管が通っています。親知らずがこの神経や血管の近くに生えている場合でも、事前にCTなどの精密検査で位置を正確に確認し、最も安全な方法で抜歯を行うことで、ほとんどの方は問題なく治療が可能です。
ごく稀に軽いしびれが出る場合もありますが、数%程度とされており、万全の準備と丁寧な手技によりリスクは最小限に抑えられます。検査と治療計画をしっかり行うことで、安心して抜歯を受けていただけます。
顎関節症について
顎関節症とは

顎は筋肉、関節、神経が集中する複雑な構造を持ち、食事や会話の際にはこれらが連動して動きます。顎の関節や周囲の組織が何らかの原因で痛んだり、動きにくくなる状態を「顎関節症」と呼びます。
顎関節症になると、顎の開閉時に音がしたり、痛みで口が大きく開けられなかったり、食べ物を噛みにくくなることがあります。また、症状によっては肩こりや偏頭痛、腕や手のしびれ、耳や鼻の不快感など、顎以外の部位にも影響が出ることがあります。
顎関節症は症状の程度に個人差がありますが、適切な処置を行えば日常生活に支障のない状態に改善することができます。重い症状のまま放置すると、顎の機能が大きく損なわれることも稀にあります。違和感や痛みを感じた場合は、早めに歯科医院で受診することが大切です。
顎関節症による副症状
顎関節症には顎周辺に見られる代表的な症状の他にも、全身の様々な部位に症状が生じる場合があります。
- 頭痛、肩こり、腰痛、首や背中の痛みなど全身の痛み
- 耳鳴り、めまい、難聴、耳が詰まった感じがするなど
- 目が疲れる、涙が出る、充血する
- 詰まった感じがするなど、鼻の症状
- 顎が上手く噛み合わない、安定しない
- 歯や舌が痛む、口が渇く、味覚異常
- 嚥下や呼吸が難しくなる、四肢のしびれ等
このような全ての症状が顎関節症が原因となっているとは限りませんが、何にせよ顎関節症の症状を感じているという時には早めに専門医の診断を受けるようにしましょう。
顎関節症の治療

顎関節症の治療で最も大切なのは、噛み合わせの改善です。
具体的には、マウスピースのような「スプリント」を上顎または下顎に装着し、上下の噛み合わせを均等に整えます。これにより、顎の関節頭の位置が正しい場所に戻り、筋肉の緊張がほぐれることで、顎をスムーズに動かせるようになります。
症状の改善に合わせて、必要であればクラウン(被せ物)や入れ歯を用いて噛み合わせをさらに調整することもあります。重度の場合には、手術による治療が検討されることもあります。